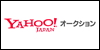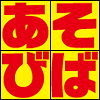こくばん
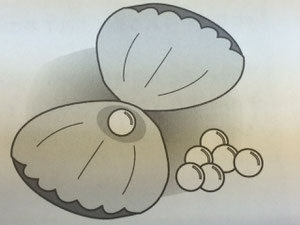
傷は真珠になる
真珠の誕生は、貝の内部組織に傷をつけることから始まります。そして、貝にとっては異物である、石のかけらなどを含ませることから成長が始まると言います。
しかし、長い年月の間に、貝の中の傷や異物は真珠に変化するのです。傷の大きさが、真珠の大きさだとも言われています。
自分を自分でセラピーでき、新しい自由を獲得した人の傷は、この真珠貝の傷と同じような成長を遂げます。どんな傷も、その人が自分の力で包み込み、それを癒し受け入れることで、他のどこにも同じものはない、唯一無二の宝石となって光を放つのです。
数回のセラピーで回復する人もいれば、何年もかかる人もいます。
しかし誰でも、真珠に変える力があるのです。長い年月のかかるものほどその玉の大きさが豊かで、その光に深みがあることは言うまでもありません。
傷は無きものにはなりませんが、こうして変化するものなのです。長年触ることも見ることもできなかった傷から、貝ガラがゆっくり開き、そこから深い光沢を放つ真珠が顔をのぞかせたとき、その宝石を見つめる目から滲む涙は、もう傷に苦しむ涙とは別の涙に変わっています。
このとき、その人の持つ潜在力に、こころから尊敬の念を抱きます。
この感動をもらう瞬間は、伴走車として一緒に走ってきたカウンセラーの役得だと感謝する瞬間でもあります。

なだ いなだ
1929年東京生まれ。本名 堀内 秀。ペンネームは「何もなくて、何もない」を意味するスペイン語からとった。作家、精神科医。53年慶応義塾大学医学部卒業。53~54年フランス留学後、慶応病院神経科や国立療養所久里浜病院などアルコール依存症の治療に取り組み、どこの病院でも閉鎖病棟(鍵のかかる患者の自由を奪う病棟)でしたが、日本で初めて開放病棟を立ち上げた方です。
『私は、病気を治して問題を解決しようとする「精神科医」ではなく、話を聴いて本人のこころを成長させて問題を解決させようとする「こころ医者」です。』と、自らを「こころ医者」と呼んだ、精神科医で作家の「なだいなだ」医学博士は、こんなことを言っています。
『医学はどんどん進歩し他の分野では高度な機械がたくさん使われるようになりました。しかし、こころの内部を見せてくれる機械は、まだ作られていません。ですから、今のところ、こころはこころにしか感じられないし、こころでしか読めないのです。ということは、患者さんのこころの読める人は、患者さん自身しかいないということです。「こころ医者」も直接には患者さんのこころを読めません。読むためには、患者さんが自分自身でまず自分のこころを読み、それを言葉で語ってくれるのを、耳を傾けて聴かねばならないし、それしか手立てはないのです。・・・・
これは、患者さんとの共同作業になります。しかし、相手が必ずしも協力的なときばかりではありません。だから忍耐力が必要なのです。ぼくは先輩から、まず徹底的に聴くことに徹しろと言われ、なんだ簡単なことではないかと思ったのですが、これがなかなか難しいことだと思い知らされました。』
さらに、『精神科医になるには、様々な分野を長年かけて勉強しなければならないが、「こころ医者」になった今、ぼくは、今まで勉強してきたことの大半が必要ない。それより、ひたすら聴くという忍耐力があれば、誰でも「こころ医者」になれる』と言う。
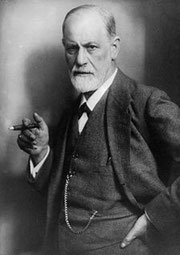
フロイト
フロイトは、「潜在意識」という存在を提唱し、哲学から心理学への流れを決定づけた心理学の父とも言われています。
彼は、自分が自分のことについて「知っている」「わかっている」と「気づいている」部分のことを顕在意識(意識)と呼びました。そしてそれは、全体のたった10%程度であろうといいます。
残りの90%は自分で自分のことに気づきもせず、わかってもいない潜在意識(無意識)だといいます。
つまり、私たちは、自分のことは自分でコントロールしているようで、実は90%という深く広い何かに、いつの間にか支配されているというわけです。
しかし、「支配されている」という受身な捉え方をしないのが、心理学の基本です。その深海のような潜在意識も自分の中の一部であるわけですから、厳密に言えば、自分の中の何かが(能動的に)支配しているということになります。
自分の言動や思いが、自分自身に指令を出すことで取っているものならば、自分を自分でコントロールさえすれば、「変えることができる」ということです。無意識の部分を少しでも意識することで、変えられないと信じていたことも、変えることができるのです。それは、「自由」を獲得することでもあり、自分の人生を自分で選んでいくという「責任」を取ることでもあります(=自律)。

アインシュタイン
アインシュタインは「常識とは、18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう」といっています。彼はこころの病気とは関係なく、科学の分野で、創造的な意見が、いかに常識によって阻まれてきたかを観察していったのでしょう。彼流のユーモアとしていったのだと思います。でも、「こころ医者」として、そこに、深い真実を見て取るのです。
小林秀雄の「常識と呼ばれている、私達の持って生れた精神の或る能力の不思議な働き」(1967版)などという、常識を絶対化、あるいは神秘化する言葉と、アインシュタインのそれとを対比してみてください。
アインシュタインによると、常識は「持って生まれる」ものではありません。「生まれてから集める」ものなのです。「不思議な働き」などではなく、単なる「偏見」です。アインシュタインのような相対論者からすれば、すべての考えは偏見です。しかし進化しつつある偏見です。
大人と同じ常識が赤ん坊にもありますか。ありません。赤ん坊に大人が持っているような常識は、まったくないといっていいほど、ありません。子供はそこから出発して、学習し、少しずつ知識を増やしていきます。それと同時に、大人になるまで、非常識を繰り返し、そのたびに大人と衝突し、いやおうなく、これが常識だというものを叩き込まれながら、育っていくのです。子供は、大人に対して、しばしば痛烈な質問をぶつけます。
「ぼくの両親は親を尊敬しろと言うけれど、親はなぜ偉いの」という質問を受け、往生しました。
「親だから尊敬しろ」というより、尊敬されたかったら、尊敬されるに足る人間に親がなればいいのです。余計なことを言わないでも素直に尊敬してくれます。ところが、尊敬されるに値しない親が、それでも親だから尊敬しろと子供に迫るから、子供は素朴に疑問を抱くのです。子供の質問がしばしば痛烈なのは、そうした大人の常識の矛盾をついてくるからです。
大人は必ずしもそのような質問には答えません。その代わりに、これが常識だと無理強いをします。
こうして親の価値観が一方的に押し付けられて、最終的に、成人する頃には、常識という名の偏見のコレクションを、いつの間にか、子供は受け継いで(潜在意識)いるのです。

「ぼくは、挨拶ができない」
解剖学専門で「脳研究」の第一人者であり「バカの壁」の著書、養老孟司さんのエピソードです。
幼いころから終わっていなかった「未完」の記憶と、50歳を過ぎてからの「完結」のエピソードが語られているのでここに掲載します。
養老さんは、4歳のときに父親を亡くしています。
お父さんは当時、20代後半から肺結核を病み、自宅で療養する生活を送っていましたが、辛そうに寝ているときにも、いつも笑いながら遊んでくれたお父さんの姿がずっと印象に残っているそうです。
そのお父さんは、養老さんが4歳のときに亡くなられ、養老さんもお父さんの臨終に立ち会いました。親戚の人から「お父さんに挨拶をしなさい」と言われましたが、なぜか、4歳児の養老さんは「さよなら」と言えませんでした。
成長した養老さんはとても内気な少年で、特に人に挨拶をするのが苦手で、近所の人と会っても挨拶ができなかったそうです。当事、人に会っても挨拶もしない神経質な少年は、親戚中から、変わり者扱いされていたそうです。
養老さんは、その後も人に挨拶をするのが苦痛で苦手だったということです。養老さんがすでに40代半ばになっていたとき、地下鉄に乗っていて不意に気づいたことがありました。「自分があんなに人に挨拶をするのが苦手だったことは、父の死と関係があるんじゃないだろうか」と。そう思ったとき、涙が溢れて止まらなくなったそうです。
養老さんは、こう語っています。
「人に挨拶をすることと、死んでいく父親に挨拶していないこととが、重なり合っていたんですね。つまり、さよならを言わない限り父は、自分の中に生き続けていることになるわけです。挨拶をやり終えていないわけですね。ということは、まだやり残していることがあるということで、その間は私の中で父は死んでいないことになるわけです。そのことが、私が人に挨拶をすることができず、苦手だったこととつながっていたんだと思います。父に挨拶をやり終えていないんだから、他人に挨拶なんかできっこない。挨拶をしてしまうと、父が本当に死んでしまい、遠くに行ってしまうから...。でも、こうした気持ちや感情は、頭の中で無意識のうち一瞬に作られてしまうことになるのですね。だから本人にもわからないのです。
私も40歳のころは、ただ父の死と何か関係があるかもしれない、と気づいただけでここまで思い至ったのは、50歳を過ぎてからです。死とは理不尽なものですよね。『あいつ死んじゃったよ、そうか...。』で済むような人間関係であればそれでいいでしょうが、親子ではそれで済むわけがない。まして子どもがまだ小さければ理不尽そのもので、死がどういうことかさえもわからないまま、突然親の死に直面させられるわけです。
私だけでなく、こうして話をしている今このときも私と同じ経験をしている子どもたちがいるわけです。」
皆さんは、養老さんのお話をどう感じ、どう捉えましたか?
養老さんの未完は「お父さんにさよならを言えていない」ということでした。「挨拶をする」=「父との永遠の別れ」という図式が養老さんのこころの中で固定化されていったのでしょう。
4歳の過去の出来事とはいえ、40歳の養老さんにとってはそれは「今ここ」での感情であり、気づきなのです。だからこそ、気づいたときに涙が止まらないのです。
大人にとっては理屈で理解できる「父の死」も、4歳の少年には「さよならと言いなさい」と言われても理解できません。お別れなんかしたくないのに、周囲の大人たちは、挨拶しろと言う。彼は「人に挨拶をしない」ことで、4歳のこころの傷を40歳になるまでずっと守ってきたのでしょう。
「さよならは言っても言わなくてもいいよ。」
「急がなくても急いでもいいよ。」
「泣いても泣かなくてもいいよ。」
その子の状態や気質に合わせて、そんなこころの猶予を与えてあげてもいいのです。
まだ4歳だった養老さんは、「ぼくはまだ、さよならを言いたくない」という気持ちだったのです。
こころの成長と共に、自然に「さよなら」が言える「時」が訪れるまで待つことが周囲の大人の役割なのではないでしょうか。
 こころのこくばん
こころのこくばん