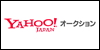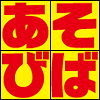テクストⅡ
アルコーリズム 社会的人間の病気
アルコーリズムとは、人間の病気として考える限り、人間のアルコールに対する自由の喪失である。そして、その中には、身体的な病気としてのアルコーリズムと、心の病気としてのアルコーリズムの二つが含まれる。身体的な病気の外側を包むようにして、心の病気がある。
つまり、アルコールの嗜癖をつくろうとする力と、その嗜癖になることに抵抗する力、それから離脱し、自由をとりもどそうとする力のぶつかり合いの中でアルコーリズムはつくられていく。
それが人間のアルコーリズムである。
○ 体の病気としてのアルコール中毒
今、目の前にいる一人の患者を見てわたしは「振戦譫妄(しんせんせんもう)」という診断名を、カルテに書きこむ。
「振戦譫妄」は、世の中では一般にアルコール中毒の典型的な症状として知られているのであるが、では、それはどのようにして起こるのか、もちろん、アルコール飲料を飲まずには、このような状態にはならない。では、どのくらいの量を、どのくらいの間飲んでいたら「振戦譫妄」を起こすようになるのだろうか。これを、わかりやすく、できるだけ単純化し、図式化して、説明してみよう。
一日量、清酒に換算して三合から四合を、毎日のように飲む。それを十年間続けると、平均的な人間は、「振戦譫妄」を起こすようになる。
もちろんこれは非常に図式的な説明で、実際には十年になる前に起こすものもいるし、それより長くかかるものもいる。体の調子にも左右されるし、一日の飲酒量がこれより少なくても起こすものがいる。しかし、それらを単純化していくと、このような結論がでる。酒類を、ある量を超えて毎日飲み、十年以上続ければ、アルコール中毒になるのは避けがたい。
一方、一回に一升飲んでも、翌日から「振戦譫妄」の症状を示すことは絶対にないし、また飲み続けても一年でそうなることはない。
それは、酒が体に一時的に入っていることによって起こるのではなく、長年の間、大量の飲酒をしてきたことによって、人間の体に病的な慢性的な変化が起こったのだ。つまり、体の病気がつくりあげられたのだ。一般の人がガス中毒などと同じように、それが中毒になることだ、と考える。そこに、アルコーリズムになるとは、長年飲んだ結果とうとう体をいためてしまったことだという人びとの持つ病気のイメージをうかがうことができる。
そこで、問題だ。わたしの目の前にいる「振戦譫妄」の症状を示した患者は一年前には、そのような症状がなかった。二年前には、もちろんなかった。逆の見方をすれば、わたしの前に一人の患者がいるということは、一年後にそのような症状を示す人間が、世の中のどこかに一人おり、また二年先にそうなるものが一人、そして十年後にそうなる人間すら、どこかにいなければならぬことを意味する。では、それらの人たちは今どうしているだろうか。
彼らは、自分が飲んべえであるとは自認している。しかし、自分はまだアルコール中毒ではないと思っている。「中毒でないのだから、自分は酒をやめる必要はない、アルコール中毒の連中は酒をやめなければならぬのが当然だ。しかし、自分はまだアルコール中毒ではないのだから飲んでもよい」。そのように考えて飲み続けているのである。それでよいのだろうか。
○ 心の病気としてのアルコーリズム
この病気を全体として眺めないものは、身体的な結果、つまり中毒症状だけに目をうばわれてしまう。これまでのアルコーリズムへの誤解はこのようにして生まれてきた。
十年目の、まごうかたなきアルコール中毒の症状を示す患者には、そこまで彼が歩み続けてきた歴史があったはずである。そして歴史的に見れば「振戦譫妄」は、数多い酒客に起こる突発的な事故ではなく、アルコーリズムの必然的な終着駅にすぎない。このようにわれわれが始めから終りまでを、全体として見つめたときに浮かび上がる病気のイメージに対応するのが、アルコーリズムという言葉だ。
では「振戦譫妄」の前の段階の人びとには、なにが見出されるだろう。わたしは、患者の人たちに、彼らが、すでに、心の病気を持っていたのだと説明している。体の病気である中毒にはなっていない。しかし、すでにアルコーリズムという心の病気であるのだと。
心の病気といってもわかりにくいかも知れない。わたしはアルコールに対する自由の失われていること、つまりアルコールにとらわれていることだと説明する。
たとえば、「振戦譫妄」を起こす瞬間に近づいた患者は、酒をやめようとすれば指がふるえる。字も書けぬし仕事もできない。酒を飲まなければ、いらいらするし、夜も安眠することができない。それゆえ、彼の心は無理やり酒をもとめさせられているのである。自分の意志で飲むのではなく、飲まずにはいられないのである。彼らは、自由を失っている。その状態を、精神医学では、嗜癖(しへき)と呼ぶのだ。その状態は、身体的にもアルコールに対する自由を失った状態であり、身体的な病気としてのアルコール中毒に隣接した状態だといったほうがよいだろう。この時期には、本人はうすうす、中毒の危険を感じている。それゆえ自分の自由の喪失に気づいていることが多い。
だが、その前に、自分では気づいていないが、しかしすでに、自由を失っている時期がある。これが問題の時期なのである。その時代には、やめようと思えば、身体的なとらわれを感じないで、一週間でも、十日でも一ヵ月でも、酒をやめていられる。だから自由であると思う。だが、そのころでも酒のうえでの失敗や、飲みすぎが理由で無断欠勤するようなことがしばしばある。経済的に、家庭に負担をかけていることも多い。また酔って暴力を振るったり、器物を壊したり、勤務先で失敗をしたり、警察の厄介になったりする。そのたびに、酒はいかんなと思う。やめようと思う。実際にもしばらくの間はやめている。だが、社会で生きていくためには、付き合いもあるし、仕事のうえで必要な酒もある。そうした状況で、失敗しない程度にとか、少しの失敗ならだれにだってあることだ、という気持ちでまた飲み始めるのである。そうした考えを持っていては、自由を失ったことを認識できるはずがない。人生の現在の瞬間しか見ることができないからである。過去と現在と未来に、等分に視線をそそがないで判断しているからだ。十日、酒をやめていることができるということから、おれは酒をやめようと思えばいつでもやめられる人間であると結論する。そしてその人たちは長い目で見れば、酒と失敗の連続から自由ではなく、そうした繰り返しの網の目にとらわれていることを見ることができないのだ。
ここでは、自覚を妨げているものとは、アルコーリズムを身体的な病気としか見ない社会一般の見方であることを、強調するにとどめよう。
アルコーリズムを全体的に眺めると、飲酒を繰り返すうちに、まず心の病気としての自由を失った状態に陥ることがわかる。さらにそこに身体的なとらわれが加わって、従来嗜癖と呼ばれていたものになるのだ。そして、必然的に離脱(禁断)症状(禁断という言葉を避けて、最近は離脱症状と呼ぶ人が増えた。正確には、禁断は酒が体から完全にぬけてから起きる症状で、離脱は酒が体から減りつつあるときに起きる症状をいう)をともなう身体的な病気としての中毒に進んでいく。アルコーリズムは時間の流れの中で進行していき、つぎつぎと新しいとらわれにおちいっていく。しかし、最初の心のとらわれは、最後までアルコーリズムの中心に残っているのである。それこそがこの病気の本質なのだ。
○ 家族の病気でもある
わたしは、患者を治療していくうえで、家族と話し合う。
そして、家族を知れば知るほど、アルコーリズムは、本人一人の病気ではない。家族全体の病気だと思うのである(最近ではそれを共依存などと呼ぶようになった)。
アルコーリックは、日本では長男と末っ子が多いと言われていて、アメリカでは、末っ子が多いと言われている。だが、それは生まれた順番に意味があるのではない。親子関係が、そのような場合に、特殊なものになりがちだからである。
そして、親子関係は、そのまま夫婦の関係に持ち込まれることもあるし、また、日本の親子同居の習慣が、大きな関係を持つこともある。
よく見られるのは、愛情の片寄った関係である。三十にも、四十にもなって、まだ母親との結びつきが一方的で、親から離れられぬものがある。結婚しても、母親が常に一緒であり、家では母親にさからうことができない。病院にも、母親に付き添ってもらってくる。そのような母親は、しばしば世の中で、「しつかりもの」といわれるようなタイプである。そして、見ていると、自分の息子ではあるが、三十にも四十にもなった男を、十四、五歳の子供のように扱っている。子供が失敗すると、本人が詫びるのではない、母親が詫びたりしている。そこに見られるのは、二人の独立した人格ではない。二人で一つの人格である。母親そのものは、しっかりもので、社会的には問題のない人物のように見え、自分で自分の欠点を自覚しないが、わたしの目からは、アルコーリズムは、この二人の共同の産物のように見える。
たとえば、ここに患者がいる。妻が入院させる必要を感じ、医師の意見を聞き、本人に勧める。本人はためらう。すると、母親が出てきて、本人が「あれだけいやがっているのだから、考えてみてやったら」と口を添える。また、今日、飲んできて、本人が「明日からは飲まぬから、もう一杯飲ませろ」と妻に要求する。妻は拒む。飲ませろ、飲まさぬで、争いが起きる。そのようなとき、母親が横から口を出す。「まあ、ともかく、明日からやめてくれればよいのだから、今晩は許してやろう」。そういう。酒を飲まない母親がアルコーリックであるはずがない。息子が、アルコーリックなのである。だが、母親の中に、アルコーリック的な心理がそのままある。母親と息子を同時に心理的に治療していく以外に、成功は得られない。だが、母親に、自分が治療を必要としている人間であると自覚させることは難しい。それが治療者として、わたしたちが直面する難問である。
また妻の中には、その母親代わりをしているものがある。夫が失敗すると、妻が夫の代わりにあやまりに行き、常にあと始末をしている。保護的であり、母親的な態度で、夫に接しているのである。この場合も問題は同じだ。
しばしば、その母親的な感情が、異常なほどの忍従の形で現れてくることもある。結婚の前から、本人の酒癖を知っていて、結婚している場合すらある。自分の愛情で、自分の献身で本人を立ち直らせてみせる、そのような気持ちで結婚する。そして努力する。あるいは、店などがある家では、本人は遊び、妻の方が店をなんとか経営しようと努力している。だが、子供ができ、十年も二十年もたつと、その情熱を失ってくる。次第に夫が重荷になり、疎ましく感じられるようになる。自分が被害者であるように思い始める。
外部から見ると、その忍耐力に感嘆したくなる。よくも耐えてきた、よく我慢できた。責められるべきものはなにもない。同情すべきところがあるだけだ。しかし、このできすぎた妻が、夫の立ち直るきっかけを、失わせていたとも考えられるのである。もし、七年前に、自分の行動が家族を破壊する危険があることを知ったら、患者は、治療をしなければならぬ、自分が立ち直らねばならぬ、という気持ちに追い込まれなかったであろうか。
もちろん、アルコーリックの中には、一見して、一般の人びとに悪妻と呼ばれているタイプの妻を持っているものもいる。まったく愛情の欠けた両親を持っているものも、ないではない。病的にヒステリックな妻や、性的に不感症の妻を持っている場合もある。その場合、患者の夫のほうが、忍従的なのである。少なくとも、酒に酔っていない間は。
こうして、家族を見ていくと、家族というものが一つの単位であり、その家庭そのものが病んでいることがわかる。家庭は全体を見なければならない。個々の人間の美徳は、全体の中で見ると、美徳でないこともある。
人間の美徳というものは、絶対的なものではなく、社会的な役割の中で判断されねばならぬもので、相手によって美徳は悪徳になる。アルコーリックの家族について考えるときには、その視点を忘れてはならない.....。

 こころのこくばん
こころのこくばん